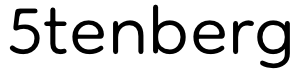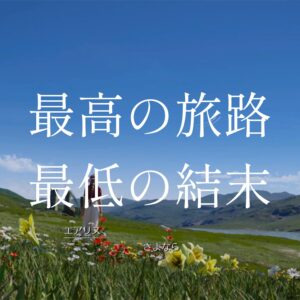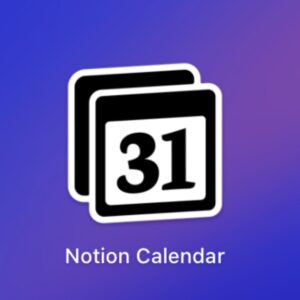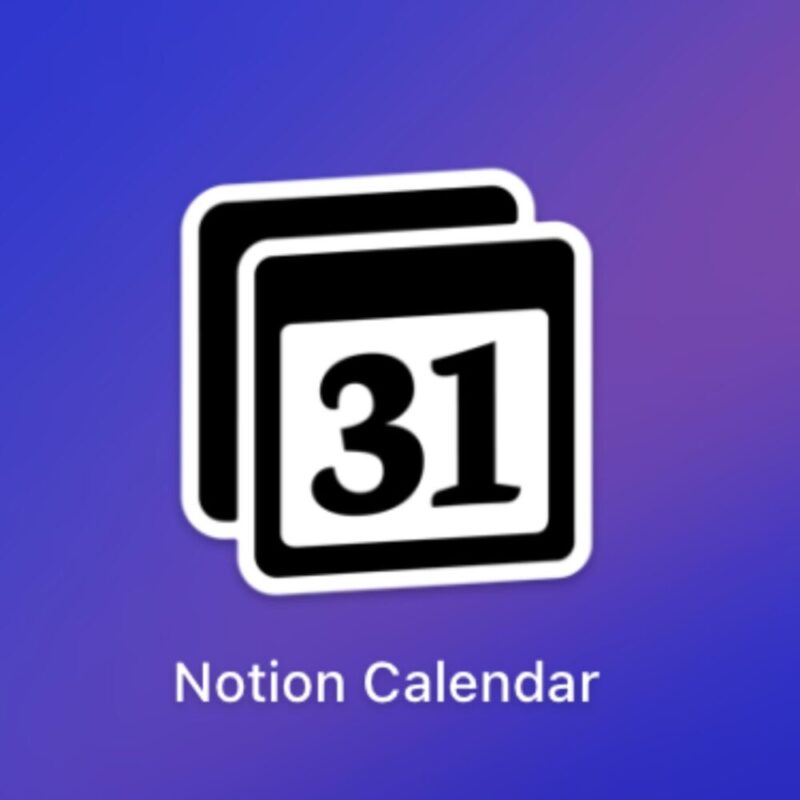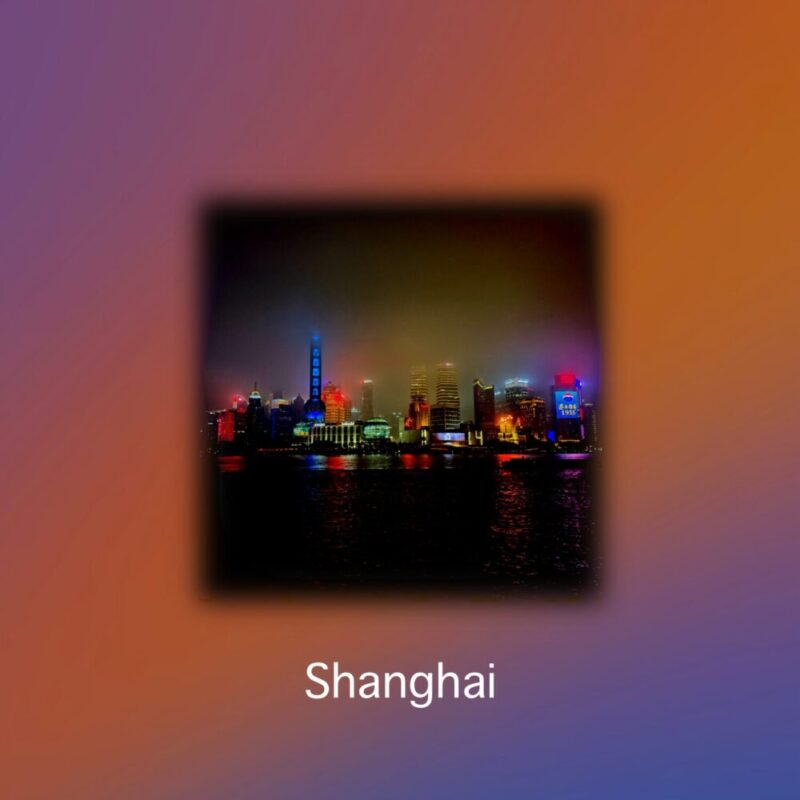上海、台湾、無計画旅【上海編】
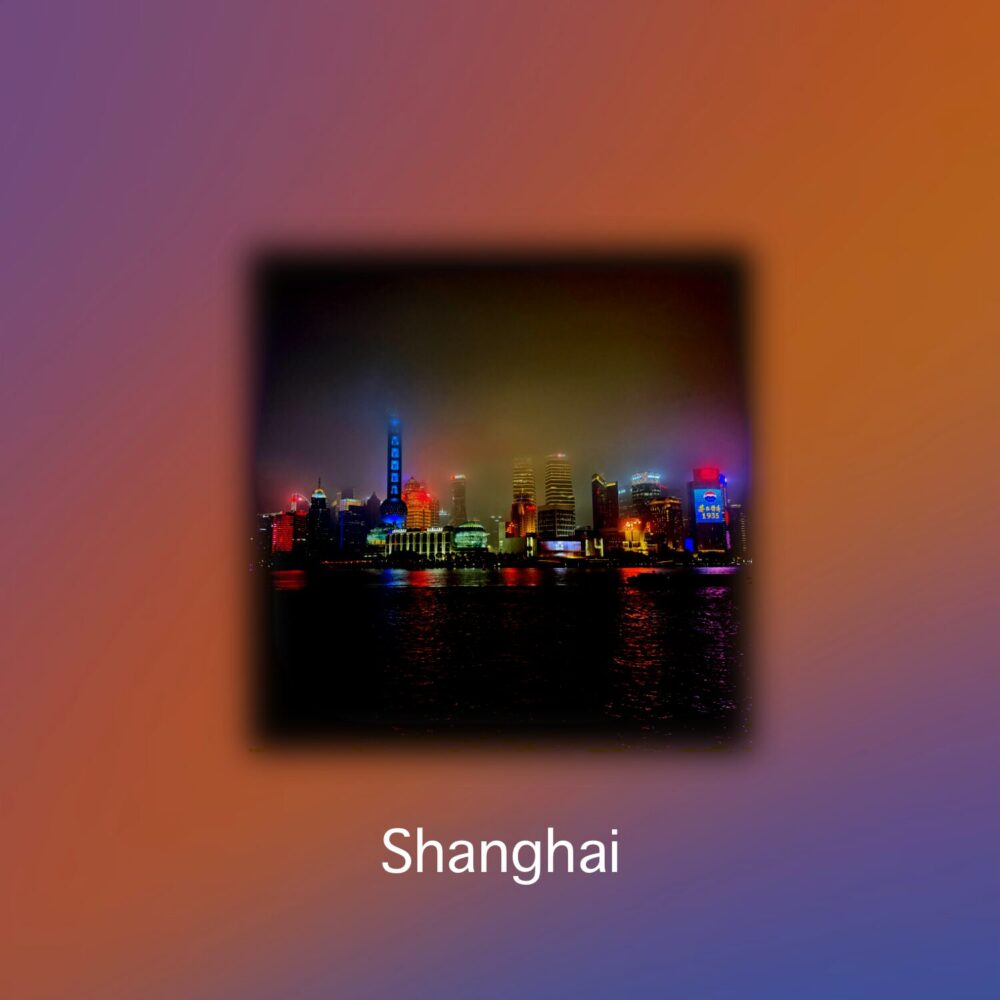
「そうだ、海外旅行に行こう」
そう決めたのは二週間前。毒にも薬にもならない予定を話し合ったのは出発前日。そして、散歩気分で旅立った当日。
懸念点は、宿、観光を含む旅のほぼ全て。唯一の余裕は、この無鉄砲加減が私がまだ若いという事の証明になること。
こうして、男3人まったく無計画な上海・台湾旅行が始まった。
一日目
上海
およそ2時間のフライトを経て、最初に降り立ったのは中国・華東地区に位置する国際都市上海。上海といえば、東方明珠電視塔、上海蟹、パンダなどが有名である。逆に言えばそれしか知らない、なぜなら無計画であるからだ。
しかし、その心配を意に介さず堂々とパスポートを提示する。しかし皆却下。宿すら決めていなかっため入国できないのだ。30分ほど空港の隅で怪しげな相談をし、ようやく審査を通過するも、またもトラブル。交通手段を調べていなかったのでホテルまでたどり着けないのだ。即座にボンクラ井戸端会議が招集される。
あなたがもし空港周辺で深刻そうな顔をしてヒソヒソ話始めたと思ったら、ワッと笑い出す怪しげな集団を見ても怪訝な顔をしないでやってほしい。彼らはあれでも結構焦っているのだ。
さて、ここで今回の弾丸旅で得た数少ない知見の一つを紹介したい。それはAlipayという万能決済アプリである。今回の無計画旅の功労賞にふさわしいのはこのアプリをおいて他にない。レストラン、公共交通機関、タクシーなどの支払いに利用でき、無計画でもある程度の精神的余裕を持って観光ができる。事実、私達は一度も中国通貨を両替せずに過ごすことが出来た。しかし、この便利さが後に悲劇を招くのだが、それはまた別の話である。

AliPayのおかげで、ようやくホテルの最寄り駅までたどり着くことができた一行。駅から出てまず初めに感じたのは、意外にも街が静かであるということ。
知っての通り中国は人口が世界2位の国である。その数なんと14億2570万人、日本のそれの10倍以上。もっとも中国の国土は日本の26倍(東京ドーム、55,609,025.77個分)であるので、単純に考えれば日本の約二分の一程度の人口密度になるわけだが、ここは上海、中国随一の国際都市である。いくら夜中だとはいえ、ある程度の賑を期待していたわけなのだけれど、なんだか気落ちしてしまう。
しかし、ホテルに行くがてら周囲を散策しているうちに、どうやらこの静けさには人口密度以上の理由があるらしいことに気づいた。よく見ると車の大半がEVであり、エンジン音がほとんど聞こえて来ないのである。車の通行量そのものは東京と同じくらいであるが、その量と音が全く比例していない。日本は案外、騒音まみれの国のようだ。
また、ホテルまでの道中(さらに上海に滞在したほとんどすべての時間において)冷たいレンズの視線を四方八方から感じることが多々あったが、これについては何も言うまい。ビッグブラザーにはできるだけ感知しないことが観光客の勤めである。
そんなことを考えながら、迷子すること30分。ようやくホテルにつく事ができた。とても安いホテルだったので価格に見合った乱雑さを半ば楽しみにしていたけれどその期待は裏切られることになる。
部屋に入ってまず目についたのは、ベッドの一部がビリビリに破けている事(もちろん、テープで補強してある)、次にテレビが昭和レトロそのままである事、そして部屋に何本かの髪の毛が残っていたこと。あとは、さほど日本と変わりはなかった。
ラーメン
観光といえば「食事」は欠かせない。むしろ観光よりこれがメインという人までいるのではないか。以前、一週間ほどタイに滞在した時はそのエスニックさどうしても舌がなれず、結局カップヌードルをすすっていたのだが、中国は東アジアであり文化圏が近い。それに何と言ってもラーメンという約束された食べ物がここにはある。
また、本日機内食しか腹に入れていない私は、空腹という偉大な調味料を日本からしこたま抱え込んできた。そう、今この瞬間のために。舞台は完璧、後は迎えに行くだけである。ホテルの向かいにあるリーズナブルで評価の高い店へ行くことにした。
。。。
ごちそうさま…いやはや、多くは語るまい、私の舌が感じ取ったのは「日本のラーメンは日本の食べ物」であるということだけだった。

しかし、(当然と言えば当然の話であるが)腹の虫がまだ収まらない。近くにFamilymartがあったのでで適当なビールと鶏の足を買ってきて食べる。ビールはホップというものがまるで感じられず好みではなかったが、しかし「鶏の足」は大当たりだった。
こりこりとした鳥軟骨のような食感に、ピリとした辛み、そして、その辛みをやさしく包み込むかのようにレモンの爽やかさ口の中にほわっと広がる。これはいわゆる「かっぱえびせんループ」に属する食べ物だ。
また、私が買ったものは中身の見えない個包装でそれぞれが包まれており、ちゅーる(猫の餌)感覚で袋からひねり出せば、今、口の中に入れようとしているものの”カタチ”が目に映る事はない。視覚的にも安心である。
後から調べてみると、この「鶏の足」は中国では割とポピュラーな食べ物だそうで「鸡爪」というものらしい。「鸡」は鶏を意味し「爪」は日本語と同じ意、つまり「文字通り」の食べ物である。辛いものが好きで、尚且つゲテモノな物にも興味があるという人は、一度試してみてほしい。味は保証するが、見た目に関しては、気分を害される方がいるかも知れないので検索する際には十分に気をつけてほしい。
「辛い鶏の足」を食べたせいか、体が熱くなってきた。エアコンをかけると、これまでにエアコンから聞いたことのないような音がする。エンスト間近のエンジンのような音だ。それに、なんだか喉が痒くなってきた。ここでようやく価格と釣り合ったわけだが、こういう場合はさっさと寝るに限る。
二日目
翌朝、早朝。眠い目を擦り「鶏の足」を頬張りながら、ようやく上海の計画を建てる。計画と言っても、めぼしい場所に印をつけただけの事であるが、全くの”無”であるよりは、いくらかマシだろう。
外灘
まず、初めに訪れたのは「外灘(わいたん)」。アヘン戦争の終結と同時に結ばれた南京条約により欧米諸国の疎開地となったこのエリアは、ヨーロッパさながらの欧風建築がズラリ立ち並ぶ一大歓楽街だ。

洋風の建築がずらりと並ぶ景色は全く壮観。事情を説明せずにこの写真を見せれば、ヨーロッパ旅行をしたのだと勘違いする人も多いのではないか。しかし、直近でフランスに行った友人からすれば「風景はそっくりだが、(車の)クラクションが足りない」らしい。
ともすれば、騒音を気にせず、疑似ヨーロッパ観光を楽しめることも「外灘」の魅力であるといえよう。しかし、外灘の魅力はこれだけではない。この建物の向かいにある運外沿いから見える都市パノラマも、素晴らしいの一言に尽きる。

写真は、夜に再度訪れた時に撮影した川沿いの夜景。あいにく当日は曇天で上部が霞んでしまっているがこれはこれで様になる絵ではないだろうか。霧による電光のにじみが醸し出すアンニュイな景色には「ネオ」だの「サイバー」といった修飾詞をついくっつけたくなってしまう。
豫園
次に、訪れたのは「豫園(よえん)」。

400年以上の歴史を持つ「豫園商城」、上海最古の茶店「湖心亭」など、上海の歴史を感じることが出来る一大観光スポットだ、ここに来なければ上海の観光とは言えない。しかし、ここでも無計画さが十二分に発揮される。いや、されていた。
というのもこの「豫園商城」と「湖心亭」の存在を知ったのは、この記事を書いている今、この瞬間であるのだ。つまり、私達は「豫園」には行ったがこの2つには全く関知していないのである。「観光スポットと言われている割には、ちょっとすごいお祭りレベルだな」と思っていはいたが、まさかそういうカラクリだったとは。
…計画は余裕を持ってに立てておくべきだ。本当に、
東方明珠電視塔
さて、気を取り直して、次に訪れたのは「東方明珠電視塔」。先程紹介した「外灘」の写真左にある変な形をした塔である。上海のことをよく知らないがこの塔は知っているという人も多いだろう。もちろん、私もその一人だ。
高さは467.9m、東京タワーの約1.5倍。球体とパイプが交わった不思議な形状は漢詩からインスピレーションを得たとのこと。塔内部には展望台も設置されており3,000円〜で見学することが出来る。
当日は内部見学こそしなかったものの、その足元まで行くことにした。

朝「外灘」から見た時もデカいと思っていたが、近くで見るとすごくデカい、いやとんでもなくデカい。見上げすぎて首、そして腰まで痛くなってくるほどだ。メガロフォビアという訳では無いが、その独特の形状も相まってなんだかちょっぴり身がすくむ。
これは余談ではあるが、この丸っこい形状を見ていると漫画「20世紀少年」に登場する「原子力巨大ロボット」が頭によぎってしょうがない。こいつは東京のど真ん中で反陽子爆弾を爆発させるため(それと博士のエゴを満足させるため)に開発されたもので、幼少期の私にとてつもない恐怖と興奮を植え付けた思い出深い存在である。もしかしたら、私が「塔」に抱いた得体の知れない恐怖も無意識にこの「ロボット」のイメージを重ね合わせていたのかもしれない。
この後、近くにある「上海科学技術館」を訪れる予定だったのだが、上海中の「博物館」と名のつくスポットがすべて休館になっていたのであえなく断念。代わりに「上海動物園」に行くことにした。
上海動物園
上海動物園は、虹橋空港の隣にある上海有数の動物園。地下鉄から出てすぐの場所にあり、800円ほどで入場できる。

動物を「可愛い」と思うのは数少ない全世界共通の感覚の一つである。しかし裏を返せばそれは、ある程度の興味関心専門性がなければ、何処の国の動物園に入っても全く同じ感想しか浮かんでこないということでもある。すなわち、一般レベルの知識量で感ずることの出来る各動物園の差というのは「動物の可愛さ」でなく、それを盛るための方法、つまり「魅せ方」や「触れ合い方」から生まれるものだろう。
よって、ここでは、そうした上海動物の動物たちに対するアプローチについての所見を2つ述べていきたい。
まず、一つ目はその広さと多様性である。上海動物園は東京の上野動物園の3倍もの敷地面積を持ち、600種、6000頭を超える動物が園内には暮らしている。体感としては少しばかり広すぎる嫌いがしなくもないが、これは私の運動不足によるものかもしれず、健康な人であれば無縁の話。それに園内にはカートも走っているので、それを利用すればそこまで広さと体力の関係を気にすることはない。
しかし、広すぎるゆえに各動物のゾーンが散り散りであり「次に何処へ行ったら良いのか」わかりにくいのには困った。園内には所々にマップが配置されているのだが、それを見ると毎度毎度すっとばしているゾーンをひとつやふたつ発見する。私の周り方が下手なのかもしれないが、とはいえ、そういう人でさえも迷わないような親切な導線がこうした施設には必要なのではないか?
などと思っていたら、どうやらこの「広大な」敷地面積にはきちんとした理由があったようだ。どうやら元々はゴルフ場であり、それが廃業した後、跡地の公園で動物が飼われるようになり、そして、その後「上海動物園」と改名されたのだという。
つまり「動物園を建てよう」としたのでなく、「動物園になった」というのが正しいのである。
それを踏まえると、広すぎる敷地面積もバラバラの動物ゾーンも納得出来る。動物園に改装する前に、ある程度の配置転換はあっただろうが、おそらく広い敷地を活かしきるためにはこうするしかなかったのであろう。
それにしても「公園」で動物を飼育し始めるというのは驚きである。日本では公園で子どもが騒ぐだけでニュースになるというのに、四千年の歴史を持つ国はスケールが違う。
二つ目は、動物と人間との距離である。著者の地元、静岡県には「富士サファリパーク」という施設がありそのTVCMのなかで「近すぎちゃって どうしよう♪」という歌詞がある。この動物との「近すぎる触れ合い」が同園の魅力の一つであるのだが、上海動物園の触れ合いは「近すぎ」を通り越して「ゼロ距離」である。
「触れられそうなくらい近い」のではなく「触れられる」のである。
これ自体はさほど珍しいことではないが、しかし、上海動物園が他と異なるのは、おおよそ触れてはいけないものまで「触れる」ことが出来てしまい、しかもそれになんの防止策も盗られていない事である。
柵の中には手を伸ばす人もいれば、ガラスをめちゃくちゃに叩く人もいる、中には、ゴミやら残飯やらを檻の中に投げ込む人すらいた。気が狂ったやつがいれば容易に動物を殺しかねない。
動物によってはその「触れ合い」がストレスになるものもいるかもしれないということを考えないのであろうか。
異国の地に来た以上、その国の文化についてどう思おうと黙っておくべきなのかもしれないが、上海滞在の中で一番のカルチャーショックがこの「距離」であった。