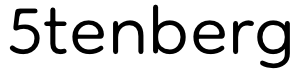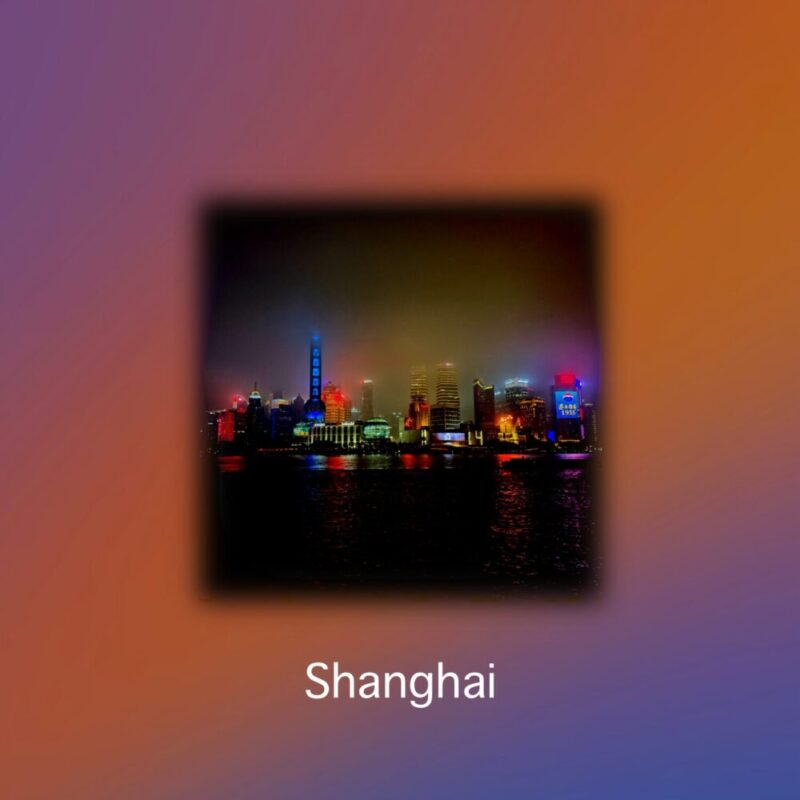タイ・バンコク最大のスラム「クロントイスラム」とは

東南アジアの心臓として発展を続けるタイ。
2025年2月の日本出国者数ランキングでは韓国、アメリカ、台湾に次ぐ4位に位置し、日本人旅行者の関心も高まりつつある。
しかし、その経済成長の裏には、依然として解決されない社会問題が横たわっている。
特に所得や教育、居住環境といった側面における社会格差は年々拡大しており、2018年に発表されたクレディ・スイスの「グローバル・ウェルス・レポート」では、上位1%の富の集中率が世界で最も高い国とも報じられた。
そして、その格差をある種体現しているのが、都市部に存在するスラムである。
今日は、それらの中でも最大かつ最古のスラム「クロントイスラム」について取り上げる。
クロントイ地区の歴史

クロントイ地区の歴史とタイの経済発展は切っても切れない関係にある。
今から遡ること約60年前、著しい経済発展の最中にあったタイ、特にその首都であるバンコクにはたくさんの人手が必要とされ、その労働需要目当てに農村部からたくさんの人々が都市部に移住してきた。
しかし、あくまで発展途上にあった当時のバンコクには、そのすべての労働力を受け入れられるほどの雇用も居住区も存在しなかった。
では、そのような「需要漏れ」した人々は一体どうしたのか?といえば
彼らは都市部にとど待った。何故帰らなかったのかと言えば、買っても結局、農村部には仕事が無かったからである。
とはいえ、待つにも「待てる場所」が必要だった。
特に、バンコクの中心を流れるチャオプラヤー川沿いにある「クロントイ港」周辺は一大スポットであった。工業化の発展とともに輸出入が拡大していったタイの港が大きなニーズを生み出していたことは想像に固くない。
次第にクロントイ港の周りに人が集まり始め、その居住域は広がっていき、いつしか、それはバンコク”イチ”のスラム街「クロントイスラム」と呼ばれるようになった。
けれど、順調に発展を遂げる都市部からしてみれば、そうしたスラムは、常にその成長と比例するように大きくなっていく目の上のたんこぶであった。
タイ政府も、この状況をただ傍観していたわけではない。
例えば、1960年代には大規模なスラム撤去・移転政策が行われた。これは文字通りスラム街を撤去し郊外に移転させるという政策であるが、「働き場所を求めてやってきた人々がいる場所 = 職場や仕事と密接した場所」というスラムの前提を全く無視したものであったため失敗。
以降もいくつかの施策が試みられ、現在では「スラムを排除する」のではなく、「スラムの生活環境を向上させる」という方針に転換されている。
また、政府や外部団体による支援だけでなく、スラム内部でも独自の組織が立ち上がり、住民自身による環境改善も進められるようになった。
こうした取り組みの結果、現在のクロントイスラムは、「スラム」と聞いて誰もがおおよそ想像されるであろう「劣悪な環境」とは異なる様子を見せている。
クロントイ地区が抱える問題

とはいえ、クロントイスラムが全く問題を抱えていないわけではない。
特に、居住権をめぐる問題(立ち退き問題)と家庭問題は、依然として深刻な課題である。
前述の通り、クロントイ地区に限らず、スラムとは「人々が勝手に住み着いた場所」である。つまり住民たちは正式な土地契約を結んでおらず、その土地に住み続ける権利が保証されているわけではない。
「いつ追い出されるかわからない」という不安は、住民たちの将来的な生活設計を大きく困難にしている。
加えて、居住空間の不足も大きな課題だ。
クロントイスラムが誕生してから長い年月が経ち、住民の世代交代も進んだ。
現在では、約10万人もの人々がこの地に暮らしているが、子どもたちの成長に必要な十分な居住スペースが確保されているとは言い難い。
さらに、子どもたちの周囲には、離婚や家族崩壊といった家庭問題、教育格差、薬物問題など、さまざまなリスクが存在しており、彼らの「今」だけでなく「将来」にまでも大きな影響を与えている。